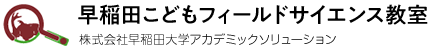プライマリークラス / ミドルクラス / アドバンスクラス
下記の9つのテーマから、7つのテーマを選んでお申し込みください(ご希望により、7テーマ以上の申し込みもできます)。
各テーマとも小学生クラス3クラス合同で催行しますが、活動のテーマ領域は同じであっても、基本的に指導内容や学習レベル、活動の実際はクラスごとに異なった扱いをしています。ただし、共通する部分では合同で活動する場合もあります。さらに一定の目的のもとに、実習地でクラス混成のいくつかのグループを作り、上級生が各グループのリーダーになり、メンバー全員が協力しあって活動することもあります。
2年生のお子さまのクラスについて
2年生のお子さまは、プライマリークラス、ミドルクラスを用意しています。 新規入会の方はプライマリークラスにご入会いただきます。継続2年目以上の方はミドルクラスもお選びいただけます。新規入会の方でもミドルクラスをご希望される方は事務局までご相談ください。

淡水プランクトンを捕る、観る生き物のつながりは、ここから始まる
①4~6人のグループに分かれて活動します。②採集は沼の足場のしっかりした安全な場所で、2人ペアになり役割を交代しながら行います。③プランクトンを入れる容器に水がいっぱいになるまで採集を続けます。④容器の中の水を濃縮してプランクトンの密度を高めます。⑤顕微鏡でプランクトンを観察します。⑥沼における生態系、食物連鎖を考えます。
- ねらい
-
プランクトン(植物、動物どちらも)は、一部のものを除いてほとんど肉眼では見えません。その微少な生き物が、実は生態系や食物連鎖の仕組みを最底辺で支えています。プランクトンの採集には専用の器具を使用しますが、それらの使い方を会得することも学習の1つです。採集はペアで進めるので、相互の協力関係を体験する良い機会にもなります。
- 実施予定地
-
埼玉県蓮田市 山ノ神沼
- 活動日程
-
- 4/13(土)
- 新
- 4/14(日)
- 新
- 4/27(土)
- 新秋
- 4/28(日)
- 新
- 4/29(祝)
- 新
- 5/5(日)
- 新秋
- 5/6(祝)
- 新
- 5/18(土)
- 新秋

甲殻類研究・エビとカニの関係解剖を通して考える
...どちらがどちらに進化した?
①磯でカニ、エビ、ヤドカリを探して採集します。②それぞれの体の特徴を確認し、記録します。特にカニの甲羅の腹側の模様に注目し、スケッチします。③別に用意したエビとカニを解剖して部位別に比較します。④部位の特徴を踏まえて、どちらがどちらに進化したのかを考察します。⑤ヤドカリについても、甲殻類の仲間としての特徴を確かめます。
- ねらい
-
同じ甲殻類ですが、エビとカニの見た目はずいぶん違います。しかし、味はよく似ていると感じます(個人差はありますが…)。エビとカニは同じタイミングで出現したのではなく、エビが先に現れて、それが進化してカニになったと言われています。そこで、磯での実習後にエビとカニを解剖して、共通する部分と異なる部分を確認し、進化の実態を考えます。
- 実施予定地
-
神奈川県横須賀市 天神島臨海自然教育園
- 活動日程
-
- 5/25(土)
- 新
- 5/26(日)
- 新
- 6/22(土)
- 新秋
- 6/23(日)
- 新
- 7/20(土)
- 新
- 7/21(日)
- 新秋
- 8/3(土)
- 新秋
- 8/4(日)
- 新

渓流で生き物を探索するいないように見えて、実はいる?
①周囲を山に囲まれた中を流れる渓流で、「たもあみ」や「仕掛け網」などの道具を使って生き物を捕ります。②それぞれの網の使い方、仕掛けるポイントなどを会得します。③上流側から川の中を歩き、隠れているサカナなどを追い出して網に向かわせます。④捕れたものは専用の容器に入れてじっくり観察します。渓流ならではの生き物が観察できます。
- ねらい
-
山間に源流がある川では、下流ほど生き物の種類や数は増えていきます。理由はエサです。支流から栄養源として豊かな水が流れ込む中流~下流にはプランクトンがたくさんいて、それを食べる小魚がいます。さらに小魚を食べる大きな魚がいて、その魚を食べるトリも現れるのです。渓流の水は澄んで冷たく、生き物がいるようには思えません。でも、いるのです!
- 実施予定地
-
神奈川県足柄上郡寄 中津川流域
- 活動日程
-
- 6/1(土)
- 新
- 6/2(日)
- 新
- 6/15(土)
- 新秋
- 6/16(日)
- 新
- 10/6(日)
- 新秋
- 10/19(土)
- 新
- 10/20(日)
- 新
- 10/26(土)
- 新秋

昆虫に親しむ思い切り網を振って、昆虫を捕る
①昆虫を観る、捕ることに特化した「ぐんま昆虫の森」で、思いきり網を振って昆虫を捕ります。②捕った昆虫は、みんなでしっかり観察します。③施設の中の昆虫の生態展示や、パネルによる学習なども体験します。なかでもチョウが飛び交う温室は必見です。④往復のバス車内では生き物のなかの「昆虫」について、さまざまな角度から考察します。
- ねらい
-
動物の仲間であるヒトは、種で分けると1種類に分類されます。いっぽう、地球上で最も繁栄している生き物と言われる昆虫は100万種を越えています。昆虫は恐竜が現れる前から地球上に存在していました。恐竜は基本的に絶滅しましたが、昆虫は生き残りました。その秘密は体の小型化です。昆虫を通して、生き物の進化や小型化の有利さを考えます。
- 実施予定地
-
群馬県伊勢崎市 ぐんま昆虫の森
- 活動日程
-
- 6/29(土)
- 新
- 6/30(日)
- 新
- 7/24(水)
- 新
- 7/27(土)
- 新秋
- 7/28(日)
- 新
- 9/8(日)
- 新秋
- 9/22(日)
- 新秋
- 9/23(祝)
- 新

食虫植物を探すなぜ、虫を食べなくてはいけないのか?
①成東・東金食虫植物群落の2つの観察エリアで、おもにコモウセンゴケとナガバノイシモチソウ、ミミカキグサ、タヌキモを観察します。②いずれも小さなものなので、拡大観察できる器具で観察します。③食虫植物が自生している環境の特徴について、実際に観察しながら考察します。④タイミングがよければ実際に虫を捕らえているようすも観察します。
- ねらい
-
植物は根から水や土中の栄養分を吸い上げ、葉で光合成を行って養分を作っています。しかし、それだけでは足りず虫などを取り込んで養分にしている植物がいます。なぜ、虫を取り込むのか…?そこには植物の生存競争があります。たとえばコモウセンゴケはとても小さく、他の植物にさえぎられて十分に光合成を行うことができません。それが虫を食べる理由の一つなのです。
- 実施予定地
-
千葉県山武市 成東・東金食虫植物群落
- 活動日程
-
- 7/31(水)
- 新
- 8/21(水)
- 新秋
- 8/24(土)
- 新
- 8/25(日)
- 新秋
- 8/27(火)
- 新
- 8/28(水)
- 新
- 8/31(土)
- 新秋
- 9/1(日)
- 新

変形菌を調べる動物でも植物でもない、不思議な生き物
①里山のあちらこちらを歩いて粘菌(変形菌)を探します。②探すポイントは太陽の日差しがあまり差し込まない、やや湿ったところです。朽ち木が1つのポイントです。③見つけたら、まずそのまま観察します。④一部のものは切りとって容器に移し、後で顕微鏡でていねいに特徴を確認・観察します。⑤粘菌という不思議な生き物について考察します。
- ねらい
-
粘菌の生活環を見ると、「胞子が発芽し増殖を繰り返す→変形体に変化し子実体を形成する→子実体が成長し胞子を飛ばす」となります。わたしたちが観察するものの多くは子実体の段階です。また、変形体は動物のように移動してエサとなるものを捕食します。生き物同士のつながりの中で、不思議な存在であるこの粘菌が担っている役割について考えます。
- 実施予定地
-
東京都あきる野市 横沢入
- 活動日程
-
- 11/2(土)
- 新
- 11/9(土)
- 新
- 11/10(日)
- 新秋
- 11/16(土)
- 新秋
- 11/17(日)
- 新
- 11/23(土)
- 新
- 11/24(日)
- 新
- 11/30(土)
- 新秋

新生代の化石さがし山の中で、海の生き物の化石を探す
①川原にある石を割る、あるいは転がっている石の表面を見て化石を探します。②見つけたものが化石かどうか、できるだけその場で判別します。③見つけた化石の特徴や種類を観察します。④化石について基本的な知識を身につけます。⑤化石を探した川原の周辺の地層なども調べます。⑥数を制限しますが、見つけた化石は持ち帰ることができます。
- ねらい
-
化石採集に取り組む地層は、いまから約1500万年前の時代の新生代第三紀の地層です。今回採集する場所は、そのころは浅い海だったと考えられています。したがって見つかる化石は、カニ、サメの歯、二枚貝、植物の一部などです。化石がどれくらい見つけられるのかは個人差がありますが、最低でも数個の化石を持ち帰れるようにスタッフが補助します。
- 実施予定地
-
埼玉県秩父郡小鹿野町 ようばけ
- 活動日程
-
- 12/7(土)
- 新
- 12/8(日)
- 新
- 12/14(土)
- 新秋
- 12/15(日)
- 新
- 12/24(火)
- 新
- 12/25(水)
- 新秋
- 12/26(木)
- 新
- 1/12(日)
- 新秋

冬の野鳥観察とフィールドサイン冬眠しない野鳥の、冬の生き方
①まず、実習地の手賀沼の近くにある「我孫子市鳥の博物館」で予備学習をします。②双眼鏡の使い方を覚えた後、観察をスタートします(双眼鏡は一人1台ずつ使用します)。③沼の周囲を歩きながら、ポイントごとに立ち止まって、ていねいに野鳥を観察します。④野鳥を観るだけでなく、野鳥の「フィールドサイン」も見つけてマップに記録していきます。
- ねらい
-
この活動では「鳥」という生き物への理解を深めることから始めます。そのため、観察前に「我孫子市鳥の博物館」で展示を見学します。展示には鳥の進化に関するものもあり、手賀沼で見られる鳥の情報も確認できるので、予備学習には好適な施設です。活動を通して、いちばん身近な野生の生き物である、鳥に対する興味関心が深まることを期待しています。
- 実施予定地
-
千葉県我孫子市 手賀沼他
- 活動日程
-
- 1/25(土)
- 新
- 1/26(日)
- 新
- 2/1(土)
- 新秋
- 2/2(日)
- 新
- 2/8(土)
- 新
- 2/9(日)
- 新秋
- 2/11(祝)
- 新
- 2/15(土)
- 新秋

地下からわき出る天然ガス泡の正体は、燃えるガスだった?!
①川沿いを歩いて水中から泡(天然ガス)が湧き出ている場所を探します。②湧き出ている場所を見つけたら、専用の道具を使って泡を袋に集めます。③袋に火をつけて、中の気体が天然ガスか確かめます(袋が燃えたら天然ガスです)。④天然ガスがどのように生まれるのか考察します。⑤天然ガスが地元で生活に利用されている実態も知るようにします。
- ねらい
-
千葉県は国内でいちばん多くのガス会社があるところです。理由は県内のあちらこちらで天然ガスが採集できるからです。自分の手で天然ガスを採集し、燃焼実験の体験を通して天然資源について考えます。小さな袋に集めた天然ガス(燃えるまでわかりませんが…)に点火すると、驚くような勢いで瞬時に燃え尽きます。これは滅多にできない貴重な体験です。
- 実施予定地
-
千葉県茂原市&睦沢町
- 活動日程
-
- 1/11(土)
- 新
- 2/22(土)
- 新秋
- 2/23(日)
- 新
- 2/24(祝)
- 新
- 3/1(土)
- 新
- 3/2(日)
- 新秋
- 3/20(祝)
- 新
- 3/22(土)
- 新秋