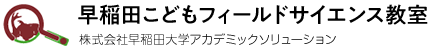プレップクラス
プレップクラスは幼稚園年長児を対象としたクラスです。活動定員は30名、1回のフィールドワークにつき最小催行人数は15名となっています。
下記の7つのテーマから、5つのテーマを選んでお申し込みください(ご希望により、6テーマ以上の申し込みもできます)。
出発解散場所
について
- 新新宿駅西口
- 秋秋葉原駅

河原の石を調べる、標本にするていねいに見る
石のある河原を歩いて、そこにあるそれぞれの石をていねいに見ていきます。漠然と見ていると石はどれも同じように見えるかもしれませんが、一つひとつていねいに見ていくと、それぞれの違いがわかってきます。見つけた石は、かんたんな図鑑を見ながら分けていき、最後は標本に仕上げて持ち帰ります。
- ねらい
-
石は、色、見た目、手触りなどに違いがあります。砂岩という石ひとつをとっても、色が微妙に違っていたり、形もさまざまです。まずは同じものをいくつか集めていき、特徴を知るようにします。これを4~5種類の石について繰り返していくと、石がどういうものかが徐々にわかってくるはずです。また、「石のできかたの違い」についても学びます。
- 予定地
-
東京都福生市 多摩川流域
- 活動日程
-
- 4/6(土)新
- 4/7(日)秋
- 4/20(土)秋
- 4/21(日)新

磯の潮だまりしっかり観察できるようになる
潮が引くと、磯にはいくつもの「潮だまり(タイドプール)」が現れます。そこに隠れている小さな生き物を、少人数のグループにわかれて観察します。また、グループのみんなで協力しながら、カニなどの生き物を採集します。採れた生き物は容器に入れて個々の特徴をよく観察し、違いや似た点などを確かめます。その後、生き物は磯に戻します。
- ねらい
-
家庭の浴槽ほどの大きさの潮だまりでも、そこにはカニ、ヤドカリ、巻き貝、イソギンチャク、ハゼなどが隠れています。この活動では、小さな潮だまりにも多様な生き物が生活していることを知り、小さな命の存在について認識を新たにし、それらに親しむようにします。また、どうして「潮だまり」のようなものが磯にできるのかについても考えます。
- 予定地
-
神奈川県横須賀市 天神島臨海自然教育園
- 活動日程
-
- 5/11(土)新
- 5/12(日)秋
- 6/8(土)秋
- 6/9(日)新

水生昆虫を調べる水に入って、生き物をさがす
川底の石の裏側に隠れている、小さな生き物を採集して観察します。実習では実際に川に入って、川底の石をていねいに持ち上げて石の裏側を観ていきます。これを繰り返していくと、数cmくらいの大きさの生き物が数種類、見つかります。小さな石を固めて巣にしているものや、石の表面をすばしこく動いて逃げるものなど、さまざまです。
- ねらい
-
川を中心とした、自然環境における食物連鎖の基本を知るようにします。水生昆虫はカゲロウやカワゲラ、トビケラなどですが、これらの成虫はサカナや鳥のエサに、幼虫はやはり水中にいる別な生き物のエサになります。小さなサカナは、より大きなサカナや鳥のエサになります。川には川の「食べる、食べられる」の関係が成立しているのです。
- 予定地
-
東京都あきる野市 秋川流域
- 活動日程
-
- 7/6(土)新
- 7/7(日)秋
- 7/14(日)新
- 7/15(祝)秋
※希望者は保護者参観にお申込できます。
(別途費用が生じます)

里山のフィールドマップづくり見つけた場所でマップ作り
里山には、池、小川、たんぼ、畑、湿地などがあります。これらを巡る小径を歩きながら、チョウやトンボなどの昆虫類をはじめ、池や小川ではサワガニやドジョウ、タニシ、カエルなどを観察します。そして、どこで、どういう生き物を見つけたかをまとめて、「里山のフィールドマップ」を完成させます。これは里山の「生態マップ」になります。
- ねらい
-
里山の生態の基本を、フィールドマップ作りから理解する活動です。サワガニは水のきれいな小川の近くにはいるけれど、濁った水の池の中にはいないこと、タニシは逆に水が濁り気味のところにいることなど、自分が歩いて確かめた事実にそって、生き方への理解を深めます。捕れるものは実際に捕って観察し、観察の後は必ず元に戻します。
- 実施予定地
-
東京都あきる野市 横沢入
- 活動日程
-
- 9/15(日)新
- 9/16(祝)秋
- 9/28(土)新
- 9/29(日)秋

サカナを網で捕る四つ手網の使い方をおぼえる
四つ手網と「たもあみ」を使い、沼の水路に隠れている小魚やエビなどを採集します。まず、四つ手網の組み立て方を練習します。次に、水路のどういうところにサカナがいるのかを知り、そこに四つ手網を沈めます。そして網にサカナを追い込んでいき、みんなで網を引き上げます。採れたサカナなどは観察容器に入れて特徴などを確かめた後、沼に戻します。
- ねらい
-
四つ手網やたもあみなどの道具を使う採集方法を体験することで、「道具の使いこなし」を覚えます。道具の役割を知り、効果的な使い方、安全な使い方を会得します。また、濁った水にも生き物がいること、姿の見えないサカナなどの習性を理解することで、生き物への関心や興味を深めます。観察では、サカナのヒレの動かし方をしっかりと観察します。
- 実施予定地
-
埼玉県蓮田市 山ノ神沼
- 活動日程
-
- 10/13(日)新
- 10/14(祝)秋
- 11/3(日)秋
- 11/4(祝)新

貝殻標本を作る形のちがいの不思議、面白さに気づく
貝殻が集中的に見られる、海岸の「貝だまり」と呼ばれる場所で貝殻を集めます。その規模はテニスコート1面よりも大きな砂浜で、無数の貝殻が集積しています。風雨にさらされて退色していたり、割れていたりするものが多いのですが、ていねいに探していくと「お宝」が見つかることも! そこで自分が気に入った貝を中心に集めて標本にします。
- ねらい
-
貝殻は大きく二枚貝と巻き貝に分かれます。二枚貝は見た目どおりですが、巻き貝がちょっとやっかいです。アワビやトコブシなどは二枚貝の片側だけのような形状をしているのに、分類上は巻き貝だったりします。このようなわかりにくいものが他にもいます。完璧な形をしている貝殻は多くないため、多少欠けていたり、摩滅していても標本の対象にします。
- 実施予定地
-
神奈川県横須賀市長井 和田長浜海岸
- 活動日程
-
- 12/21(土)新
- 12/22(日)秋
- 1/18(土)秋
- 1/19(日)新

カエルのたまご見つける、さわる、調べる
冬枯れの里山を歩いてカエルのたまごをさがします。さがすのは池や水が溜まっているところで、この時期にたまごを産むのはアカガエルのなかまです。冬眠を中断してたまごを産むと、また冬眠に戻ります。なんとも不思議な生態です。ちょっと難しいですが、なぜ寒い時期にわざわざたまごを産むために起きるのか、その理由を考えてみます。
- ねらい
-
たまごを産むことは子孫を残すための大切な行動です。しかし天敵に襲われたりして、産んだたまごがすべてふ化することはまれです。ではどうするか…?天敵が活動していない時期をねらえば安全です。アカガエルは、そうしたことから真冬にたまごを産むのです。透明な膜に包まれたカエルのたまごは、触ると独特の感触で、不思議な存在感があります。
- 実施予定地
-
東京都あきる野市 横沢入
- 活動日程
-
- 3/8(土)新
- 3/9(日)秋
- 3/15(土)秋
- 3/16(日)新